パーキンソンについてなんでも相談できる
窓口をご用意しています
2025.01.04
パーキンソン病とドーパミンの関係

#女性の病気
#男性の病気
ドーパミンの役割
ドーパミンは、脳内で神経細胞同士が情報を伝達するために使われる神経伝達物質の一つです。 私たちが手足を動かすとき、脳の運動を制御する部分がドーパミンを使って、筋肉に「動け」という指令を伝えます。 この働きのおかげで、私たちはスムーズに歩いたり、物を持ち上げたりすることができます。 しかし、パーキンソン病になると、脳の中にある「黒質(こくしつ)」という部分にあるドーパミンを作る神経細胞が徐々に減少します。 この神経細胞が減ることで、脳内のドーパミン量が減少し、運動を制御する仕組みがうまく働かなくなります。 その結果、手足の震え、筋肉のこわばり、動作が遅くなるなど、パーキンソン病特有の症状が現れるのです。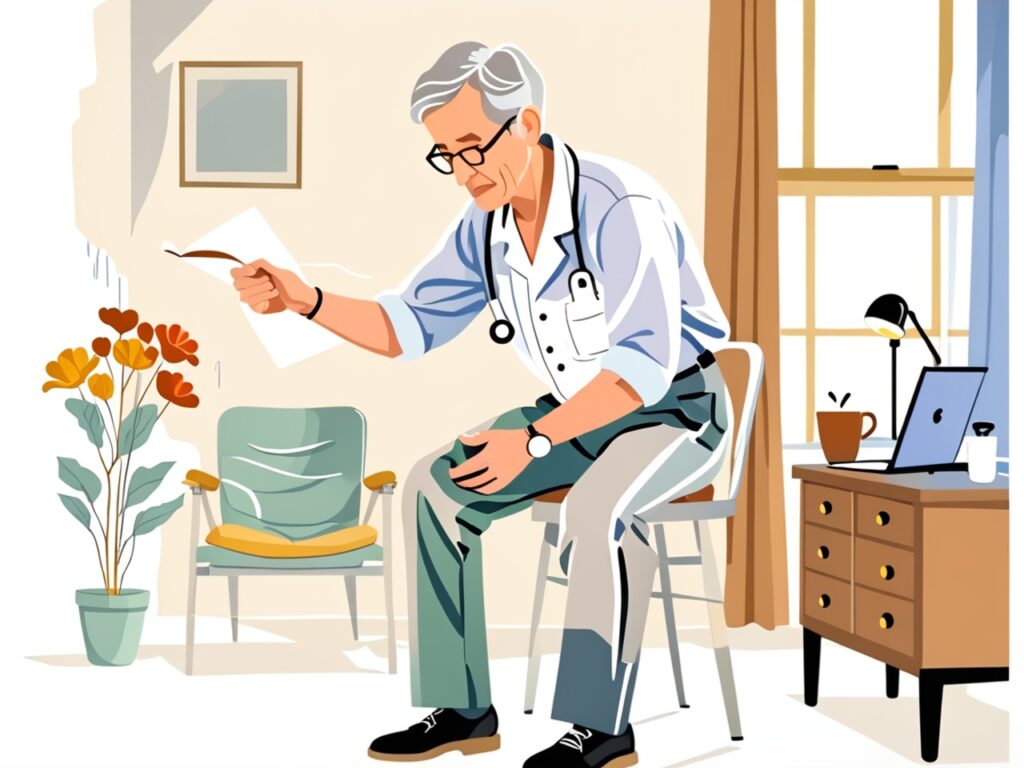
パーキンソン病でのドーパミン不足の影響
- 運動機能への影響 ドーパミンが不足すると、私たちの体はスムーズに動かなくなります。 特に、手や足の動きが遅くなったり、震えが生じたりします。 これは、脳からの「動け」という指令が正しく伝わらないためです。例えば、歩行がぎこちなくなり、歩き始めるのに時間がかかったり、途中で足が止まってしまったりする「フリーズ現象」も、ドーパミン不足による影響の一つです。
- 精神的・感情的な影響 ドーパミンは、運動制御だけでなく、感情ややる気にも影響を与えます。そのため、ドーパミンが不足すると、うつ症状や無気力、意欲の低下が見られることもあります。 パーキンソン病の患者様が疲れやすくなったり、興味を失ってしまうことがあるのは、このドーパミンの減少が関係しているのです。
ドーパミンを補う治療法
パーキンソン病の治療の主な目的は、不足しているドーパミンを補い、症状を和らげることです。 ドーパミン自体を直接補うことは難しいため、ドーパミンの前駆物質を使って脳内でドーパミンを増やす治療が行われます。 主な治療法には次のようなものがあります。
主な治療法には次のようなものがあります。
- レボドパ(L-ドーパ) レボドパは、ドーパミンの前駆物質であり、脳内でドーパミンに変わります。 レボドパは、パーキンソン病の治療において最も効果的な薬物であり、運動症状を大きく改善します。 しかし、長期間使用すると薬の効果が不安定になり、「オン・オフ現象」(症状が突然良くなったり悪くなったりする現象)が起こることがあります。
- ドーパミンアゴニスト ドーパミンアゴニストは、ドーパミン受容体に直接働きかけ、脳内でドーパミンのように振る舞う薬です。 レボドパほど強力な効果はありませんが、効果が長持ちしやすく、初期のパーキンソン病治療に使用されることが多いです。
- その他の治療 ドーパミンの分解を抑えるMAO-B阻害薬や、COMT阻害薬も、ドーパミンの効果を持続させるために使用されます。 これらの薬を組み合わせることで、症状をより安定させることが期待できます。
ドーパミンの将来の治療に向けた研究
現在、ドーパミン不足を根本的に治療する方法はありませんが、ドーパミンを増やすための新しい治療法が研究されています。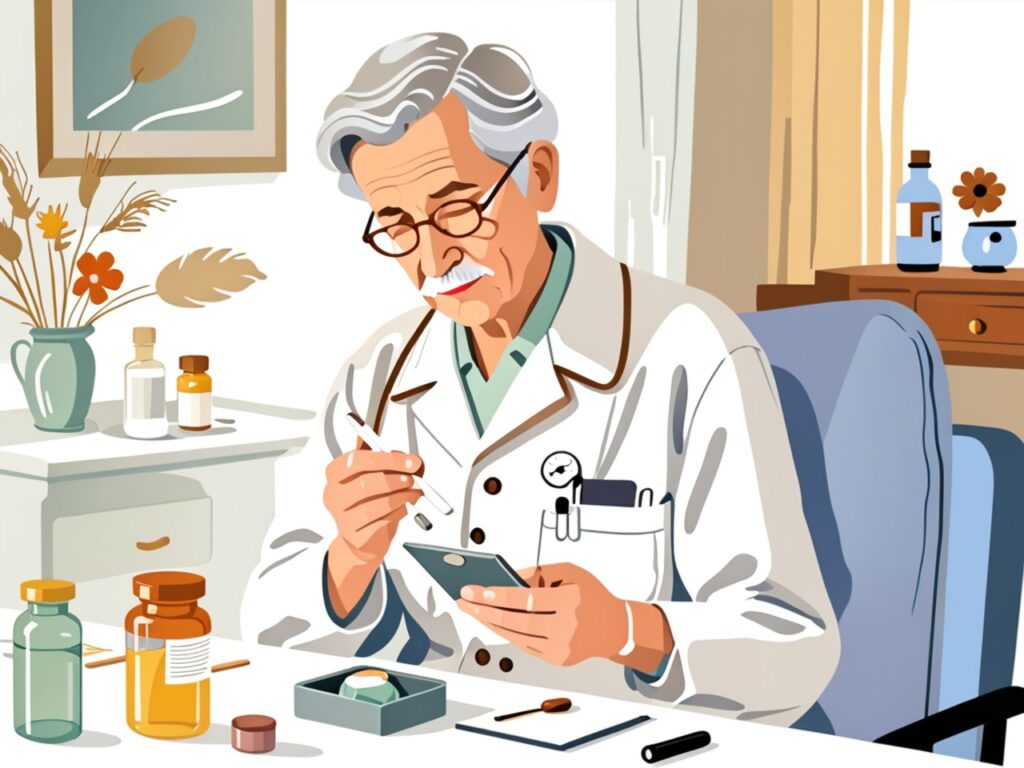
- 幹細胞治療 幹細胞を使って、ドーパミンを作り出す神経細胞を再生する研究が進んでいます。幹細胞を脳に移植することで、新しいドーパミン産生細胞を作り出し、パーキンソン病の症状を軽減することが期待されています。
- 遺伝子治療 ドーパミン産生を促進する遺伝子を導入する治療も研究が進んでいます。この治療法では、脳の神経細胞にドーパミンを作り出す能力を回復させることを目指しています。
結び: ドーパミンを理解してパーキンソン病と向き合う
 パーキンソン病の症状の多くは、脳内でドーパミンが不足することが原因です。
ドーパミンは、運動を制御するために重要な役割を果たしており、その不足は体の動きや精神状態に大きな影響を与えます。
しかし、適切な治療を受けることで、症状をコントロールし、生活の質を維持することが可能です。
今後もドーパミンを増やす新しい治療法の研究が進むことで、さらに効果的な治療が期待されます。
パーキンソン病と共に生きるためには、ドーパミンの働きを理解し、医師と相談しながら最適な治療法を選ぶことが大切です。
パーキンソン病の症状の多くは、脳内でドーパミンが不足することが原因です。
ドーパミンは、運動を制御するために重要な役割を果たしており、その不足は体の動きや精神状態に大きな影響を与えます。
しかし、適切な治療を受けることで、症状をコントロールし、生活の質を維持することが可能です。
今後もドーパミンを増やす新しい治療法の研究が進むことで、さらに効果的な治療が期待されます。
パーキンソン病と共に生きるためには、ドーパミンの働きを理解し、医師と相談しながら最適な治療法を選ぶことが大切です。 
